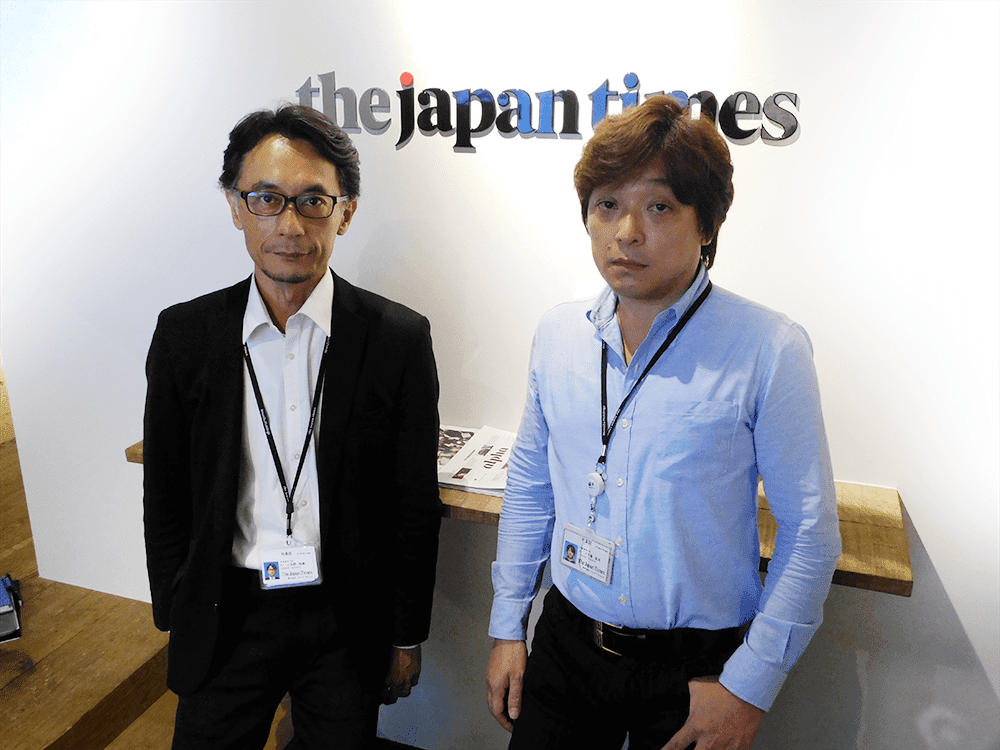世界で読まれる日本最古の英字新聞「The Japan Times」とは
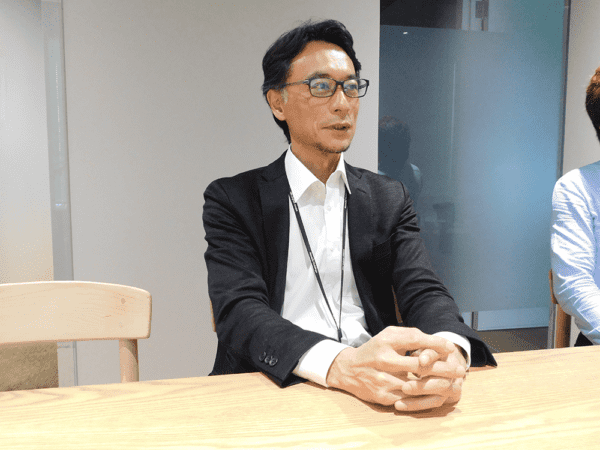
執行役員補佐経営管理局次長
兼 経営推進部長 大野 裕幸 氏
株式会社ジャパンタイムズは、主に日本国内の情報を世界に迅速かつ、正確に伝えていくのをミッションとして、1897年に設立された日本最古で最大の英字新聞社だ。
同社が発行する「The Japan Times」の創刊当時、文明開化によって西洋の文化が日本に入り、それまでの制度や習慣は大きく変化していた時期だった。当時、外国人から見た日本は、まだ近代化には程遠いとみられており、そうした状況を見た創業者たちが、“日本のイメージをしっかり伝えたい”と考え設立された。
海外へ事業展開していた企業や財界人から、資金面での協力を得ながら、“日本から英語で発信する”ことを大切に今日まで運営されてきた。
こうして始まった日刊英字新聞「The Japan Times」は、創業当時は日本に住む外国人が主な読者だったが、現在は世界中に広がりを見せている。それはインターネットの普及によってWeb版を公開したことにより、多くの人が最新の情報をいち早く手に入れられるようになったことも大きな要因だろう。また、同紙は災害発生時に訪日中の外国人や、家族が日本に訪れていることで不安な日々を過ごしている人のために無料開放し、最新の情報を得られるよう配慮している。そういった細やかな心配りも魅力の一部なのだ。
同社の執行役員補佐 経営管理局次長 兼 経営推進部長 大野 裕幸氏は最近の本紙について次のように教えてくれた。
「日本に対しての興味は年々明らかに急増しているので、どのように日本の姿とその魅力を伝えれば、日本への理解につながるのかというのを考えながら、一民間企業ではありますが、毎日情報を編集して発信しております。アクセス数は月間800万PVで、アクセス数は伸びてきています。」
サーバ料金の急激な増加と保守問題
『The Japan Times』のWeb版は、100周年を迎えた97年頃に公開され、月間800万PVを集めている。1日100本ほどのニュースを24時間365日、国内外にいる編集者によって更新されており、大きな事件やニュースが起きた時には、1分でも早く掲載されるよう運営されているため、安定したWebサイト運営は大前提となる。
サーバにはAWSを採用し、AWSパートナーである保守会社にAWSの設定と保守を委託してきたが、運営を続けていくうちにトラフィックが増加し、Webサイトの表示速度が遅くなってしまった。そこで、サーバスペックを上げることで対処したがその分コストが上がってしまった。また設定変更によってデータトランスファー費が20倍近くになってしまったことがあった。そんな中、土日に障害が発生し、対応が遅れてしまったことから、保守会社の変更を考えるようになる。
もともと保守を委託していた会社はビジネスタイムでの保守のみで、夜間や土日は対象外となっていた。この時のことを踏まえ、委託先の変更には土日夜間も含めた対応をしてくれる保守会社にすることにし、以前提案を受けていたプライム・ストラテジーならばその条件を満たしておりサーバ費用も含まれるのでコストの変動を気にする必要が無いことも魅力に感じ、委託することにした。
⇒KUSANAGI導入前に自社サイトも高速化するかどうかチェックしてみる
⇒高速化を実現したKUSANAGIを見てみる
⇒保守コストの削減と24時間365日の保守体制を実現できるマネージドサービスを見てみる
コストは2/3に減少、少ないサーバでも安定した稼働が可能
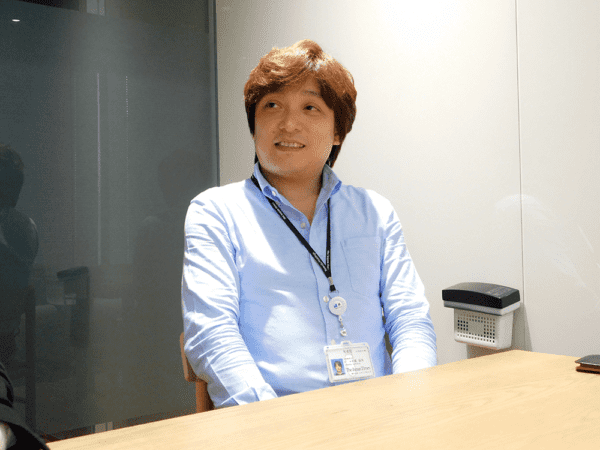
編集局 メディア制作部長 千振 弘光 氏
移設は、サーバをAWSのままにし、「KUSANAGI」を導入することにした。同サイトのデータベースは大きく、かなりの作り込みをしていたため、深夜から早朝にかけての作業を行った。導入後1週間程度は問題が発生したが、それも即時行ったチューニングによって、すぐに快適な状態になったという。
編集局 メディア制作部長 千振 弘光氏は導入後について次のように語っている。
「以前、Apacheからnginxに変えたときには、正常に動かなくなった機能がたくさんあったので、今回の移設でも何かあるだろうなとは思っていました。結構作りこんでいて、データベースも膨大なので。でもすぐにチューニングしてもらって、今は快適に動いていると思います。速度も改善され、海外担当者からは何か問題があったらすぐに連絡が来ますが、それもないので大丈夫なのでしょう。『KUSANAGI』はとにかく不思議ですね。前の環境の時に、データベース用のサーバには大きいものを3台、Webサーバは支援用を含めて3台用意していましたが、今回の移設で、小さいサーバになって台数も少なく、スケールも1/4程度のサイズです。なんで動いているんだろうなと不思議です。コストは、サーバ代金と監視、保守会社の3点のトータルで考えると2/3程度になったと思います。」
⇒KUSANAGI導入前に自社サイトも高速化するかどうかチェックしてみる
⇒高速化を実現したKUSANAGIを見てみる
⇒保守コストの削減と24時間365日の保守体制を実現できるマネージドサービスを見てみる
今後も、より正確なニュースをスピーディーに届けていく
今後、「The Japan Times」は、どのように運営されていくのか。大野氏はこう答えている。
「日刊の英字紙が看板商品として中核をなしているので、すべてを電子化するわけではありません。紙の読者を増やしていきたいですね。そのためには、より正確なニュースをスピーディー、かつ、『The Japan Times』というブランドを、一人でも多くの人に認知してもらうためにもデジタル化は欠かせないです。現場としても、毎日新聞は作りますが、デジタルファーストというポリシーは持っています。デジタルも紙も、きっちり育てていきます。」